システム内は英語名が基本..かも。
システム設計をする際、様々な名称を決める必要が出てきます。
.
データベースの名称、データ項目名や画面の項目名、インターフェースのファイル名やフォルダー名称、プログラム内の一時ワーク項目名など、直接ユーザに見えない部分で様々な名称を決める必要があると思います。
.
.
これらの名前、皆さんはどんな命名をされていますか?
.
私は様々な失敗、苦労の末、結局、英語アルファベット名にするのが一番安全で確実という結論に至りました。
.
以前はインターフェースのフォルダー名に漢字名を使ったり、DB項目名をURIAGE_SURYOなどのローマ字で設計したりしていました。 漢字フォルダー名は一部のOSから正しく参照や書き込みができない障害がありました。既に稼働中のOSや文字コードを変更する事はほぼ不可能で苦労しました。DBや項目名称も一部の海外関連会社に参照を許可した際、全く意味が通じず仕方なくViewを作成したりして対応しました。
.
考えてみれば設計時にすべて英語名にしておけば、何も問題にはならない事で、それ以降全て英語名で定義するようにしています。
.
英語の長い単語には大抵標準の短縮名があり、例えば数量はquantityですがqtyでも全く問題ありません。売上数量ならsales_qtyと命名しています。
日本の事をJAPと短縮して恥をかいた事もありましたが、それも全て勉強でした。
.
.
考えてみればITは米国で発展した技術で、英語を使う事が基本です。最近では日本語も問題なく使えるように思いますが、今でもプログラミングを含め全て英語で記載するものです。
.
また、現状あるシステムを含め、将来メンテナンスする人は100%日本人とは断言できないはずです。ビジネスがグローバルに展開している現在、漢字やローマ字の命名で良いのでしょうか。
.
私は社内のシステムであってもシステムの中身は英単語で記載する事をお勧めします。
.
所詮、ITで使う英単語は限られていますし、英語の勉強にもなり、システムの将来性も広がりますよ。
,
,
2025年6月6日
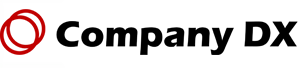
コメントを残す